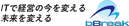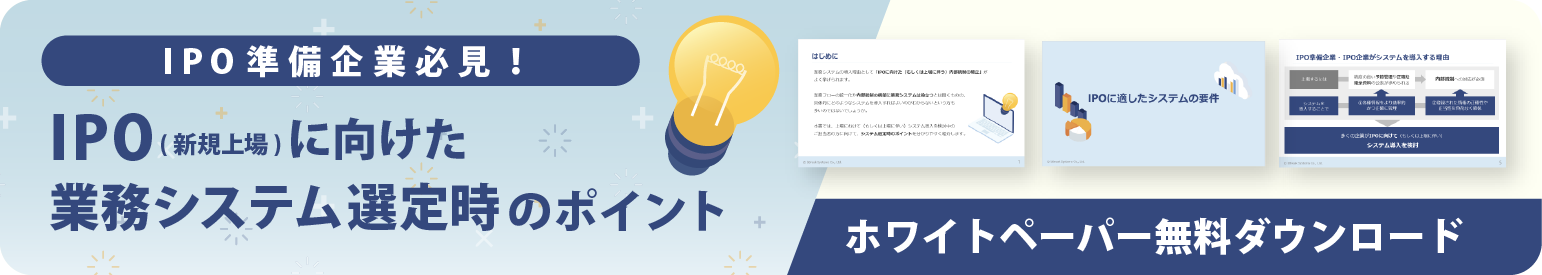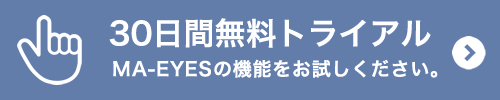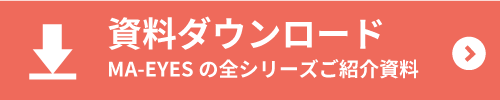ERPにはどんな種類があるのか?費用に見合う効果があるのか?
そもそも自社に合ったシステムをどう選べばいいか分からない...
そんなERP導入に関するお悩みをお持ちではないでしょうか。
本記事は、ERPシステムの意味などの基本的な解説に加えて、IT業、SIerやコンサルティング業などの「プロジェクト型ビジネス」に焦点を当て、導入の具体的なメリット・デメリット、そして自社に合ったシステムの選び方までを徹底解説します。
近年はSaaS型で手軽に利用できるERPも増え、中小企業でも導入が加速しています。 20年間ERPシステムを開発・販売している当社(ビーブレイクシステムズ)が、最新のERP動向と、導入で失敗しないための実践的なノウハウ をお伝えします。
ERPシステムとは
ERPシステムとは企業の経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)を一元管理し、業務効率と意思決定のスピードを向上させるためのシステムです。(ERPは「Enterprise Resource Planning」の略称です。)
ERPが誕生した背景
従来、企業のシステム導入は、経理、販売、人事といった部門ごとのニーズに合わせて個別に行われてきました。その結果、それぞれの部門で最適なシステムが導入され、各業務の効率は上がりました。
しかし、会社全体で見ると情報はすべての部門をまたいで繋がっています。個別のシステム管理では、部門間でデータの二重入力や集計の手間が発生してしまい、経営層がタイムリーに全体像を把握できないという問題がありました。
この「情報のサイロ化(孤立)」を解消し、業務プロセス全体を統合するために登場したものがERPシステムです。
当初、ERPは高額な費用とリソースが必要で、大企業しか導入できないというイメージがありましたが、近年はクラウドで利用できるものも増えており、中小企業でも手軽に利用開始できるものが主流になっています。
プロジェクト型ビジネスにおけるERPの必要性
中でも、プロジェクト単位で動く事業(システム開発会社、SIer、コンサルティング、広告業など)において、この情報の分断は深刻な問題となります。
売上や工数、仕入れといった原価情報がバラバラに管理されることで、プロジェクトのリアルタイムな収支(利益の着地見込み)が見えづらくなり、赤字プロジェクトの発生や発見の遅れという致命的な結果を招きます。
当社もシステム開発・SIerの企業であるため、プロジェクト収支管理の現場の悩みを熟知しています。 だからこそ、経営をリアルタイムで可視化するERPの必要性を強く感じています。
ERPと基幹システムの違い
ERPと基幹システムは、どちらも企業の核となる業務を支えるシステムですが、その目的とカバーする範囲に大きな違いがあります。
基幹システムは「部門最適」
基幹システム(個別システム)とは、会計、販売、生産管理といった企業の特定の「部門の核となる業務」に特化して最適化されたシステムです。
これらのシステムの主な目的は、特定の業務領域における処理の正確性や処理速度の向上にあります。そのため、特定の部門内では高い効率と精度を発揮しますが、他の部門とのデータ連携は手動やバッチ処理に頼ることが多く、全社的な視点での最適化は困難です。
ERPシステムは「全体最適」
一方でERP(Enterprise Resource Planning)は、会計、販売、人事、生産管理といった企業のあらゆる部門の業務プロセスを単一のデータベースで統合管理するシステムです。
ERPの目的は、個別の業務効率化ではなく、企業全体の情報の一元化による経営層のスピーディな意思決定や、部門の壁を越えた業務フローの最適化です。
プロジェクト収支管理における違い
プロジェクト型ビジネスでは、部門最適の基幹システムの場合、売上は販売管理、人件費は勤怠管理、経費は会計システムなど、データが分散するため、プロジェクトごとのリアルタイムな正確な収支(利益)の把握は困難です。プロジェクトの終盤になって初めて赤字が判明するケースも少なくありません。
一方、ERPはプロジェクト単位でリアルタイムに収支を集計できます。これにより、現場のプロジェクトマネージャーから経営層までが常に最新の採算状況を把握でき、赤字になる前に対策を講じることが可能になります。
ERPの主な導入形態(クラウド/オンプレミス/ハイブリッド)
ERPの導入形態は、主に「クラウド型」と「オンプレミス型」に分けられますが、その大きな違いはサーバーを置く場所です。それぞれにメリットとデメリットがあるため、貴社の予算や利用人数、ITリソースに応じて最適な形態を選択する必要があります。
クラウドERPの特徴
クラウドERPは、ベンダーが提供するサーバー環境でシステムを利用する形態(SaaS)です。そのため導入企業は物理的なサーバーの購入や管理が不要です。
近年は「Fit to Standard(フィット・トゥ・スタンダード)」という考え方が主流となり、その結果としてクラウド型(SaaS)の導入が加速しています。 Fit to Standardとは、カスタマイズはせずに自社の業務をERPの標準機能に合わせて変革していくという導入アプローチで、カスタマイズの自由度が比較的低いSaaSとの相性が良いため、特に中堅・中小企業でクラウド導入が増えている大きな背景となっています。
クラウドERPのメリット
- ERPの標準機能(ベストプラクティス)に業務フローを合わせられる
- 初期コストが低い、または不要で、比較的安価に利用開始できる。
- サーバー管理やシステム保守が不要で、IT部門の負担が軽減される。
- 短期間で導入でき、すぐに利用を開始できる。
- インターネットさえあればアクセスでき、テレワークや出張中でも業務が進められる。
クラウドERPのデメリット
- 自社の複雑な業務フローに合わせた自由なカスタマイズが難しい。
- 導入は自社主体で行う必要がある。
- データやセキュリティの管理がベンダーに依存する。
オンプレミス型ERPの特徴
オンプレミス型ERPは、自社のサーバーにシステムを構築・導入する形態です。
オンプレミス型ERPのメリット
- 自社独自の複雑な業務に合わせて自由にカスタマイズできる。
- 導入はベンダー主体でサポートが手厚い。
- 自社のセキュリティポリシーに基づき、厳密なデータ管理が可能。
- 利用人数が多い場合に、長期的にみるとクラウドサービスよりも安価になる可能性がある。
- 同時接続数が多い場合でも、メモリを増やして対応可能。
オンプレミス型ERPのデメリット
- 初期導入コストが高額になる。
- サーバー構築や保守・運用を自社で行う必要があり、ITリソースの負担が大きい。
- 導入期間がクラウドと比較すると長く、その分の人的リソースが必要。
SaaS+が実現するハイブリッドな導入形態
「オンプレミスのコストや保守負担は避けたいが、ERPの導入を自社で行えるか不安」というお悩みを抱える企業は多いです。
当社のMA-EYES
SaaS+(サースプラス)は、クラウド型の導入でありながら、導入から稼働までを当社が責任を持って伴走するのが最大の特徴です。
ERPシステムの導入が初めてであったり、リソースが割けない、自社に定着するかわからないなどの不安がある場合も、20年間ERPの導入に携わっている当社のエンジニアがサポートしますので、安心して導入できます。
また、豊富なパラメーター設定に加えて、オンプレミスと同様にカスタマイズをすることもできるため、汎用的なパッケージでは管理が難しいといったケースにも対応可能です。
プロジェクト型ビジネス向けERPの主な機能
ERPは様々な機能を備えておりますが、ここではSIerとしての経験から重要だと考える、プロジェクト型企業に必要な機能を中心にお伝えします。製品によって大きな違いがあるため、実際には自社に必要な機能が備わっているか確認しましょう。
管理会計
販売や購買などのデータと連動することで、プロジェクト別、部門別、顧客別など、様々な切り口での収益分析を可能にします。月次決算を待たずにいつでも正確な着地見込みを把握できます。
仕訳データや決算書の作成だけでなく、配賦計算や、プロジェクトごとの詳細な損益計算書(P/L)を自動で作成できるため、データに基づいた迅速な意思決定を支援します。
プロジェクト管理
案件の引き合い段階から、見積作成、受注、売上計上といったプロセスを一元管理します。実行予算(プロジェクト原価)を正確に立て、それを実績と対比させることで、プロジェクト収支管理を実現します。
プロジェクト管理で特に重要なのは、要員(リソース)のアサインと原価予測の連携です。
- 案件獲得の初期段階で、必要な人的リソースや外注費を具体的に計画し、プロジェクトに割り当てます。
- このアサイン計画に、担当者ごと・役割ごとの単価を紐づけることで、受注前にプロジェクトの採算性を高精度で予測することが可能になります。
実績データはリアルタイムで予定(予算)に紐づくため、プロジェクトの開始直後から赤字の予兆を捉えることができ、手遅れになる前に対策を講じられます。
購買・経費管理
外注、仕入れ、経費精算といった支出を一元管理します。特にプロジェクト型ビジネスでは、外注費が原価の大半を占めることも多いため、どの支出がどのプロジェクトに紐づくかを正確に管理することが重要です。
発注・経費申請の段階でプロジェクトと紐づけし、承認フローと連動させることで、すべての支出を自動的にプロジェクト原価として割り当てます。
工数・勤怠管理
従業員の勤怠や給与計算を行う機能です。プロジェクト型ビジネスにおいては工数管理が非常に重要です。誰がどのプロジェクトにどれだけの時間を費やしたか(工数)を正確に把握し、これを労務費としてプロジェクト原価に自動で反映させます。
現場のメンバーが日々の工数入力を行うだけで、プロジェクト別労務費を自動計算するため、月次決算を待たずにリアルタイムでプロジェクトの利益率を把握できます。
ERPの導入メリット
ERP導入のメリットは多岐にわたりますが、情報の一元管理によって企業の経営判断の質を高め、収益を安定化させることが最大の目的です。
ここではERP導入のメリットについてひとつずつ丁寧に解説していきます。
業務効率アップ
ERPの導入は、部門をまたぐデータ連携を自動化することで、Excelへの二重入力や集計作業といった間接業務を大幅に削減します。
二重入力の削減は、時間短縮だけでなく、ヒューマンエラーによる請求漏れ、原価計上ミスといった収支に直結するエラーを防ぐ役割を果たします。
特に工数、経費、外注費が自動的にプロジェクトに紐づく仕組みは、月末のプロジェクト原価の集計作業をゼロにします。
そのほか、様々な業務が自動化し、業務効率化に貢献します。例えばこれまでメールで行っていたワークフローが自動で担当者に通知がいくようになったり、発注した内容が承認されると自動的に支払へデータ連携するなどが挙げられます。
スピーディーな経営判断
従来のシステムでは、各部門のデータ集計に時間がかかり、経営層が最新の正確な情報を把握できるのは月末や月次決算後でした。ERPに日々の業務を登録していくことで、手間をかけずに必要なデータをリアルタイムで確認できます。
プロジェクト型ビジネスでは、どのプロジェクトが予定工数を超過しているか、どの段階で赤字に転じる可能性があるかを瞬時に把握できます。これにより、要員配置の変更や外注費の見直しといった手を打つことが可能となります。
内部統制の強化
ERPは、各種データの入力・変更に厳格なルールと承認フローを組み込むため、データの信頼性が高まり、内部統制の強化につながります。また、財務データの正確性が確保されることで、経営判断の品質が向上し、投資家や株主などからの信頼性も高まります。 上場準備を行っている企業が、IPOの内部統制要件を満たすためERPを導入する場合も多いです。
▶上場に向けた社内管理体制の確立をスピード実現した事例「株式会社BTM様」
ERPの導入時の課題・デメリット
ERP導入にはメリットも多いですが、高額な投資と全社的な変革を伴うため、課題やデメリットも存在します。
この章では、ERPの導入時の課題とデメリットについて、具体的な例を挙げて解説し、その対策方法にも触れます。
ERP導入を検討する際の参考となれば幸いです。
高額なコストと長期的な負担
ERPで特にデメリットとなるのは導入にかかるコストです。システムの選定・構築のための初期費用(イニシャルコスト)に加え、ライセンス費用や保守費用、導入支援や研修などにかかるランニングコストも考慮する必要があります。
選択するシステムの種類やクラウドか否かによって費用は大きく変わり、オンプレミスの場合は、初期導入費用やサーバーなどの調達・管理コスト、稼働後の保守費用などがかかります。クラウドサービスの場合は定期的なサブスクリプション費用や利用人数などデータ容量に応じた費用がかかります。
ERP導入の際には、これらのコストを適切に比較・評価し、長期的に見て(5年間程度)利益があるかを判断することが大切です。初期導入コストが高くても、運用・保守費用が低いシステムを選ぶことで、長く利用することでトータルコストパフォーマンスが向上する場合もあります。
業務フローの見直しや修正が必要
現状の業務フローをERPの標準機能に合わせて最適化することは、ERP導入の目的の1つです。 しかし、組織が長年培ってきた業務フローや作業方法を見直すことは簡単ではありません。従業員の学習コストや変更への抵抗、業務の一時的な混乱など多くの課題があります。
導入失敗の最大の原因は、現場が「今までのやり方」に固執し、システムを利用しないことです。特にプロジェクト収支管理においては、工数入力や経費精算のルール変更が現場の反発を招きやすく、データ入力が疎かになることで、リアルタイム可視化という最大のメリットが失われるケースが散見されます。
業務フローの見直しや修正をするには、従業員の理解が必要です。経営層からの明確なビジョンの共有と十分な説明をし、変更の理由やメリットを理解してもらうこと、また適切な研修やサポート体制を構築することが重要です。
自社にマッチしたシステム選定が難しい
市場には、国内外を問わず多種多様なERPシステムがあります。それぞれ異なる機能を持ち、価格も様々なので自社の特定のニーズに最適なシステムを探すことは容易ではありません。 各システムの比較検討に多くの時間を要しますが、最終的に自社に完全にマッチしたシステムが選べる保証はありません。
適切なシステム選定には、知識と経験を要します。自社で対応するのが難しい場合は、専門的なコンサルティングサービスやサポートを利用するというのも選択肢のひとつです。費用はかかりますが、知見のあるプロにサポートしてもらえるのは安心です。しかし、完全に任せきりというわけにはいかず、あくまでサポートです。自社の業務内容を理解している人は必要なので、それなりに工数がかかることは避けられません。
そのほか、RFIなどベンダーに情報提供を依頼するための文書を作成するという方法もあります。作成には手間がかかりますが、一度作成をすればベンダーから回答をしてもらうことである程度自社に合うシステムを絞り込むことができます。
自社に合うERPシステムの選び方4選
ERP導入の課題で述べた通り、市場には多種多様なシステムが存在するため、自社に完全にマッチするシステムを探すのは容易ではありません。特に、プロジェクト型ビジネスは業種・業態ごとに収支管理のプロセスが複雑に異なるため、汎用的なシステムでは「痒い所に手が届かない」という状況に陥りがちです。
お金と時間をかけてERPを導入したにもかかわらず、自社に合っておらず定着しないまま終わってしまうといったことを避けるためにも、ERPを選定する際に気を付けたい4つのポイントについて解説します。
業界・業務特化型であるか
自社に合わない業務フローのERPを利用するには、大幅なアドオン開発が必要になります。 自社の業界に合ったシステムを利用することで、最適な業務フローに合わせることができます。また、ベンダーも業界への理解があるため導入や要件定義等がスムーズです。
プロジェクト型ビジネス特化のERPであれば、工数管理や原価計算の仕組み、外注費管理、契約形態の多様性など、独自の商習慣に必要な機能があらかじめ標準搭載されています。
柔軟な設定変更(パラメーター設定)が可能か
「Fit to Standard」が主流とはいえ、自社独自の業務プロセスすべてを汎用システムに合わせることは難しいです。 ここで重要になるのが、「パラメーター設定による自由度」です。
カスタマイズは、システムコードに手を加えるため、高コストで導入期間が長くなり、システムアップデート時の弊害にもなります。
一方、パラメーター設定による自由度の高いERPであれば、短期間・低コストで自社に最適なシステム環境を実現できます。
将来的な業務の変更に柔軟に対応するためにも、「どこまでをパラメーター設定で変更できるか」を詳細に確認すべきです。
外部システムとの連携可否
ERPは各部門の業務を統合しますが、財務会計システム、給与計算システム、MA(マーケティングオートメーション)ツールなど、専門性の高い外部システムは残すケースがほとんどです。そのため、それらの既存システムとスムーズにデータ連携できるかは重要なポイントです。
連携可能な場合は、どのように実現するのかについても確認が必要です。APIなどを利用したリアルタイムなデータ連携(自動連携)が標準で用意されているか、夜間のバッチ処理であったり、手作業での連携が必要な場合もあります。
自社が現在利用している、あるいは将来的に導入を検討している外部システムのリストアップを行い、ベンダーに具体的な連携実績と手法を確認することが重要です。
セキュリティがしっかりしているか
ERPシステムは経営の中核を担う情報システムであり、重要なデータを一手に担います。そのため、ERPを選定する際は、システムのセキュリティ体制が自社の求めるレベルに達しているかを確認する必要があります。
機密情報が外部に漏洩しないようにデータ暗号化がされているか、誰がどのプロジェクトの、どのデータにアクセスできるかを人ごと・部門ごとに細かく設定できるかなど確認が必要です。
企業の情報資産を守るためにも、セキュリティ対策が十分に施されているかを確認しましょう。
導入形態や特化業種を選択可能!
自由度の高いERP「MA-EYES」資料ダウンロード

- MA-EYESの導入形態を比較
- 自由度の高さ
- MA-EYESのプロジェクト管理
ERP導入成功のためのロードマップ
ERP導入は、数ヶ月から数年に及ぶ全社的なプロジェクトです。失敗を避けて確実に成果を出すためのERP導入のステップを解説します。
システム化の目的・課題・要望を明確にする
まずは現状の問題を特定し、解決したい経営課題や目的を明確にします。
- 既存の業務フローやデータ管理方法を棚卸しし、非効率な点や属人化している業務を洗い出し
- 各部門の担当者へヒアリングし、要望をまとめる
実際にシステムを導入する段階で、対応できない要件が見つかりトラブルになる可能性もあるため、
手間がかかる作業ですが、事前に準備しておきましょう。
ここでの洗い出しをしっかりしておくか否かで、システム導入の成否が決まると言っても過言ではありません。
システム化の方針を決める
ERPの製品選定にあたり、導入形態はクラウドにするのか、オンプレミスにするのか。
カスタマイズはせずに標準機能にあわせるのか、特定の業務だけはカスタマイズを許容するのか、などの方針を定めておきます。
そうすることで、話を聞く前に製品をある程度絞ることができるため、効率的に検討ができるでしょう。
システム選定とトライアル
要件をもとに候補を比較検討します。話を聞く会社は4-5社に絞ることをオススメします。実際に試用(トライアル)をして、自社の業務が管理できそうかを必ず確認しましょう。
プロジェクト収支管理を重視する場合は、「案件単位の損益管理」「工数・原価連携」などが標準で備わっているかもチェックしましょう。
また、決定したシステムの要件等を、経営陣含む各関係者に周知しておくことも必要です。最終決定時に、認識が異なるといった理由からシステムの導入自体が白紙になるというケースもあります。
導入準備と移行計画
システム選定後、本番環境への移行計画を立てます。 データ移行やユーザーアカウントの整備、操作権限の設定など、運用開始に向けた準備を段階的に進めましょう。
特にプロジェクト型ビジネスでは、進行中の案件データをどのタイミングで新システムに移すかが重要です。移行時期を誤ると、収支管理にズレが生じるリスクがあります。 移行作業はベンダーと連携し、テスト環境で入念に検証することが不可欠です。
定着フェーズの計画を立てる
本稼働がゴールではなく、「定着」まで見据えて計画しましょう。 マニュアル整備や研修をしつつ、ベンダーのサポートも最大限に活用しましょう。
ERPについてまとめ
本記事では、ERPの基本的な概念から、導入のメリット・デメリット、そして失敗しないための選び方までを解説しました。
ERPシステム導入にはコストが必要ですが、プロジェクト型ビジネスにおいては、業務効率化のためだけでなくリアルタイムな収支(原価)を可視化し、赤字プロジェクトを未然に防ぐという重要な役割を果たします。
当社は長年に渡りプロジェクト管理に特化したERPを販売しており、導入事例も豊富にございます。お気軽にご相談ください。