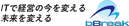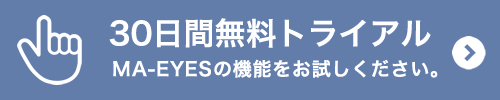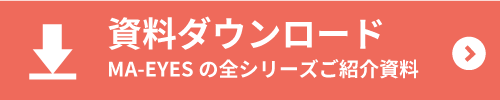近年、業務効率化は特に注目されています。その背景には少子高齢化による人材不足があり、限られた人材で利益率を維持・向上させるために効率化が求められています。また、働き方改革の推進により、ワークライフバランスを重視した働き方が求められ、残業の削減や働く場所の自由化などを推進する企業が増えています。外部環境やニーズの変化のスピードが増す中で、競争力を向上させるために業務の効率化が増々重要になっていくことでしょう。
本記事では、業務管理についての基本的な考え方や抑えておきたいテクニック、進め方を紹介します。
業務効率化とは
業務効率化とは、企業や組織において日々の作業をより効果的に進めるために、業務プロセスやステップを見直し、無駄やムラを排除して効率を高める取り組みを指します。
具体的な手法として、ワークフローの見直し、無駄な作業の自動化、使用ツールやシステムの最適化などが挙げられます。効率化のアイデアは幅広く、小さな改善から大規模な改革まで多岐にわたります。例えば、業務分担を再検討したり、時間管理のノウハウを学んだり、システムによる業務の自動化することなど様々なアプローチがあります。
業務効率化に取り組むには、まず現状を把握し、無駄がどこにあるかを見極め、その上で具体的な効率化策を実施します。ただし、現状の方法を大きく変更する場合、関わる人が多くなるため、全社員が協力し合うことが重要です。
業務効率化を行うことで、リソースの最適な配分と全体の生産性向上に貢献し、生産性の高い業務に集中できる時間が生まれます。結果として企業全体のパフォーマンスが向上に繋がります。
業務効率化と生産性向上の違い
業務効率化と生産性向上はどちらも企業の成長に必要なものですが、その目的や手法には違いがあります。
業務効率化とは、現在の業務フローや手法を再評価し、無駄を取り除くことで効率を上げる取り組みのことです。一方、生産性向上は、労働時間や労働力単位あたりの成果を最大化することを主な目標としています。
業務効率化を行うことで、結果として生産性が向上することもありますが、必ずしもそうなるとは限りません。これらは別のものを指しているため、両者を区別して適切にアプローチすることが必要です。
業務効率化の必要性
業務効率化が必要となる理由はいくつかあります。
- 人手不足に対応するため
- 仕事量の増加に対応するため
- リモートワークや働き方改革の推進に対応するため
- 長時間労働を防止し、社員の健康を保つため
- 社員のモチベーションを向上させるため
コロナ禍により働き方が大きく変わった今、業務効率化の取り組みは労働環境の改善を実現するためにも重要です。
業務効率化で得られるメリット
業務効率化は、短期的な成果だけでなく長期的な企業の成長にも繋がります。この章では業務を効率化することのメリットについて紹介します。
時間や人件費などのコストが削減
業務の効率化により一つの業務にかかる時間やリソースを減らすことで、同じ時間内でより多くの業務を遂行できるようになります。そのため、残業代などのコスト削減などに繋がり、人手不足の解消にも寄与します。
従業員のモチベーションアップ
業務効率化により無駄な時間が削減され、働きやすさが向上することで達成感ややりがいを感じやすくなります。労働環境の改善によりストレスが軽減され、従業員のモチベーションアップに繋がります。また、効率的に仕事を終えることで自由な時間が増えるため、ワークライフバランスを重視した働き方が可能になり、従業員の満足度アップにも貢献します。
組織の生産性が向上
作業環境を整えることで、従業員の集中力が高まり、高いパフォーマンスを発揮できます。これにより、高品質な成果を短期間で提供することが可能となり、企業全体の生産性が向上します。効率化によって得られた時間やリソースを活用し、新しい業務やプロジェクトにも取り組むことができ、イノベーションや成長の機会が増えます。
今日から使える業務効率化のアイデア
この章では今日から使える業務の無駄を省き効率化する方法やアイデアを紹介します。やみくもに取り組むのではなく、自社の状況や目的に合わせて選択しましょう。
定型業務の自動化
定型的で単純な作業はRPAツールやExcelのマクロ、VBAなどを活用することで、自動化することが可能です。例えば単純なデータ入力や書類の作成、計算作業といった業務を自動化することができます。システムで自動化することで手作業によるエラーや時間の浪費を大幅に削減でき、人的資源を他の重要な業務に集中させることができます。人間と違いシステムは24時間稼働することも可能なため、初期コストはかかるものの、長期的にはコスト削減と業務効率の向上が期待できます。事前に業務の見直しを行い、自動化対象を洗い出しましょう。
ワークフローを見直す
ワークフローを改善することで、業務プロセスのボトルネックを解消し、全体のパフォーマンスが向上します。
ワークフローの見直しには、まず現状の業務フローをフローチャートや図を用いて可視化し、無駄な業務や非効率なフローはないかを検討します。例えば、承認者の数やその適切性、二重チェックの無駄がないかなどを確認しょう。ワークフローは定期的な評価と改善をすることが望ましいです。
マニュアルの作成
業務手順をマニュアル化することで、作業の標準化を推進します。新しい担当者への教育がスムーズになり、コスト削減に繋がります。また、新しいシステムや機材の導入時には、事前にマニュアルを備えておくことで、スムーズな運用開始を実現できます。
マニュアルは読み手が業務を容易に理解できるように作る必要があるので、図、表などを用いて視覚的にわかりやすくすることが求められます。作成のコストはかかりますが、準備をしておくことで長期的に利用でき、業務効率に貢献します。
テンプレートの作成
テンプレートの作成は業務効率向上に有力です。例えば、報告書や社内連絡文のテンプレートを事前に準備しておけば、書類を一から作成する手間を大きく省けます。メールのテンプレートも同様に、作成しておくことで迅速な返信が可能になります。テンプレートを組織全体で共有することで一貫性が保たれ、業務の質が向上します。
作業のスピードアップ
ご自身の日常業務で作業のスピードを上げられないか検討することも重要です。Windows等のショートカットキーを駆使することで、作業がかなり早くなります。よく行う作業はショートカットキーがないか調べてみましょう。意外に便利なものが組み込まれていることがありますよ。
また、成果物を作るときは、最初から完璧を目指すのではなく、ざっくりと方向性がわかる状態でお客様や上司に確認をもらい、適切なフィードバックを得ることも有効です。これにより無駄な作業や手戻りを防止することができます。
作業のスピードアップには日々の努力やスキルアップも重要であり、例えばタッチタイピングのスピードを上げるなど自主的な取り組みが業務効率の向上に寄与します。
納期を決める
タスクに具体的な期限を設けて取り組むことも有効です。集中力が高まり、全体的な作業効率が向上します。また、期限を設定することで、優先順位を自然に決定でき、緊急性の高いタスクが後回しになるリスクも軽減されます。
納期が決まっていない場合でも自主的に納期を定めましょう。時間を意識して業務に取り組むことで、先延ばしの防止や効率的な作業が期待できます。
優先順位を付ける
すべてのタスクを同時に処理しようとすると、無駄が生じやすく効率が低下します。まず、タスクを重要度と緊急度で分類し、優先順位を明確にしましょう。
さらに、スケジュール表を活用し、具体的な時間内に行う業務を設定するのも効果的です。たとえば、「何時から何時までに○○の作業をする」といった具合に細かく設定します。これを習慣化すれば、スケジュール通りに進めるために何時までに特定の業務を終了するべきかを自然と逆算できるようになります。
休憩を適度に挟む
効率的に業務を進めるためには、適度な休憩を取ることが欠かせません。長時間作業を続けると疲労が溜まり、パフォーマンスの低下を招きます。ある程度の時間ごとに短い休憩を挟むことで、気分をリフレッシュし、集中力を再び高めることが可能です。また、深呼吸や軽いストレッチも心身のリフレッシュに非常に効果的です。適切な休憩を取り入れることで、高いパフォーマンスを維持することができます。
整理整頓をする
職場環境の整理整頓をしましょう。物理的なデスクだけでなく、パソコンのデスクトップやファイルフォルダーの整理も重要です。整理整頓することで必要な資料やファイルに素早くアクセスできるようになり、無駄な検索時間を減らします。整理された環境は、集中力を高め、生産性向上にも大きく寄与します。
ミスを減らす
ミスを削減するには、まずミスが発生しやすいポイントの特定をしましょう。そして、それぞれの対策を講じます。対策としては見直しのプロセスを設けることや、ダブルチェック体制を導入することなどが挙げられます。また、作業手順を明確化し標準化された方法で進行することで、ミスのリスクを抑えられます。日頃から注意深く業務を行うことを社員全体で意識し、共有することも重要です。納期設定についても、見直しのための余裕を含めた計画を立てましょう。
メールチェックは最小限に
効率的な業務運営のためには、メールチェックの頻度を極力減らすことが重要です。多くのビジネスパーソンは、作業中にメールの通知を見てすぐに確認してしまいがちで、集中力がそがれ時間の浪費を引き起こします。特定の時間帯に一括してメールを確認するようにすることで、集中力を保ちながら、効率よくメール処理を行うことが可能です。メールチェックの時間を少なくし、より重要なタスクに専念できる環境を整えましょう。
現状に満足しない
業務効率化は一度きりの取り組みではなく、持続的な改善が求められます。日常業務の中で「この方法が本当に最適なのか」と常に問いかけることが重要です。現行のやり方に甘んじることなく、常により良い方法を探求することで、業務は徐々に効率化されます。
社員一人ひとりが自分の業務に対して改善点を見つけ出す意識を持つことが理想的です。技術の進歩や新しいツールの導入など、環境の変化にも柔軟に対応し、より優れた業務フローの構築を目指しましょう。
業務効率化のステップ
業務効率化を効果的に推進するための手順を紹介します。
業務の棚卸をする
業務の効率化を図るには、まず現状の業務の棚卸しをしましょう。現状どのような業務があって、どのようなフローになっているのかを把握します。全社的に業務改善をする場合は社員へのヒアリングや現場観察をしっかりと行い、業務全体の状況を正確に把握することが必要です。
改善点の洗い出し
現状把握の後は、業務プロセス内のムダや非効率を洗い出すフェーズになります。それぞれの業務にどれくらいの時間がかかっているか、どのプロセスで無駄が発生しているかを分析しましょう。不具合や効率低下の箇所を特定したら、それらの改善ポイントを明確化します。
この際、現場の社員からのフィードバックを活用することが非常に有効です。現場の視点から得られる情報は、実行可能で有効な改善策を見つけるための貴重な手がかりです。さらに、データ分析を活用して問題点を数値的に示すことで、具体的な改善策をより明確に把握することができます。
改善箇所の優先順位を決める
改善点が明らかになったら、それぞれに優先順位をつけます。業務の重要度や影響範囲、実行の難易度を基に評価します。フォーマットを活用し、各改善箇所を一覧にすることで、視覚的に優先順位を確認しやすくなります。また、改善の実施手順や担当者を事前に記載しておくことが推奨されます。こうすることで、担当者間のコミュニケーションが円滑になり、改善活動がスムーズに行えるようになります。
改善方法を検討する
改善箇所の優先順位が決まった後は、以下の改善の8原則に従って改善方法を検討します。
- 廃止:そもそもその仕事が必要か、なくせないかを検討
(古い資料のメンテナンスを廃止するなど) - 削減:頻度、回数、時間、人数、項目、分類、量などを減らすことができないかを検討
(経由部門を少なくする、会議の頻度を減らすなど) - 容易化:作業しやすく、簡単にできないかを検討
(繰り返し使う文章をテンプレート登録する、よく使う資料をすぐにアクセスできるようにするなど) - 標準化:単純化、ルール化できないかを検討
(誰もが作業できるようにテンプレートを作成する、ナレッジを共有するなど) - 計画化:より計画的に短時間でできないかを検討
(認識の違いで無駄な手戻りが発生しないように事前の確認をしっかりするなど) - 分業分担:業務分担を見直して作業を効率化できないか検討
(特定業務を外注する、得意な部署へ任せるなど) - 同期化:待ちの時間が発生しないように平行して作業ができないかを検討
(いつも催促されてしまう作業を優先的に終わらせるなど) - 機械化:ソフトウェアやシステムなどを活用して効率化できないかを検討
(Excelのマクロを利用する、RPAやITシステムを導入するなど)
改善方法が決まったら、具体的にどのように改善するのかまで落とし込み、実施します。
効果検証を行う
業務改善を実施した後は、その効果を検証しましょう。改善策が期待通りの成果を上げているかを確認するために、定量的なデータやスタッフのフィードバックを収集します。データ分析を行い効果が確認できた部分や改善が必要な点を把握し、効果検証の結果を基にさらに改善を続けることで、持続的な業務効率化が可能になります。
業務効率化に便利なサービス・ツール
ITツールやサービスを活用して業務効率化する方法も有効です。組織全体で効果的に業務を進めるためには、適切なツールを選択することが重要です。この章では、業務効率化に役立つサービスやツールを紹介します。
アウトソーシング
アウトソーシングは、特定の業務を外部のプロフェッショナルに委託する方法です。特に営業やコールセンター業務は、内製化よりもアウトソーシングの方が、コスト効率が高まるため効果的です。これにより、自社のリソースを本来注力すべきコア業務に集中させることが可能となります。例えば、営業活動を専門の外部企業に依頼することで、自社の営業スタッフは戦略立案や重要な顧客対応に集中できるようになります。
また、委託先の専門知識やノウハウを活用することで、企業の生産性や競争力を強化することにも貢献します。
ERP
ERP(Enterprise Resource Planning)は、企業のリソースを一元的に管理するシステムです。販売管理、プロジェクトの進捗確認、勤怠管理など多岐にわたる業務を統合的に管理します。特にクラウドベースのERPは、リアルタイムでのデータ更新が可能であり、各部署間の情報共有をスムーズに行います。これにより、業務プロセスの全体的な効率化が図られ、無駄が大幅に削減されます。 さらに、プロジェクトごとの予実もリアルタイムで確認できるERPもあるため、適切なリソース配分と業務の見直しが容易になります。データベースの統合により、1箇所でデータを入力すれば、他のシステムでもリアルタイムに反映されるため、重複入力の手間が省け、効率的なデータ管理が実現します。
RPA
RPA(Robotic Process
Automation)は、パソコン上で行われる業務を自動化する技術です。この技術を使うことで、例えばデータ入力のような単調な作業をロボットが代行し、業務効率を飛躍的に向上させることが可能です。RPAを導入することで、作業ミスの減少や作業時間の短縮が期待されます。特定の条件に合わせた処理や、複数のシステム間でのデータ移行も自動化できるため、複雑な業務プロセスも簡素化されます。特に定型的な業務が多い部門において、高い効果が得られます。その結果、リソースをより戦略的な業務に割り当てることができるようになります。
代表的なツールとしては、ウィンドウズPCにインストールして使用できる「WinActor」が知られています。
スクリーンショット機能
スクリーンショット機能を使って画面上の情報をキャプチャし、手軽に共有することでコミュニケーションがスムーズになります。特に、マニュアル作成の場面では視覚的な情報が役立ちます。また、エラー報告やデザインのレビューなどでも、スクリーンショットがあれば視覚的に伝わり、対応がスピーディに行えます。パソコンにデフォルトで備わっているショートカットキーを使えば、いつでも簡単にスクリーンショットを撮ることが可能です。
カレンダーやチャットのリマインド機能
カレンダー機能およびチャットのリマインダー機能を活用することで、連絡漏れやタスクの見落としが発生しにくくなります。例えば、チャットツールによるリアルタイムのリマインドは、重要なタスクやミーティングを忘れることなく、スムーズに業務を進行させることができます。また、共有カレンダーを使うことで、チーム全体のスケジュールが把握しやすくなり、調整や計画が円滑に進められます。
パソコンのメモや付箋機能
パソコンの付箋アプリやメモアプリを活用することで、アイデアや重要なタスクを簡単に記録することができます。例えば、必要な情報や重要なメモをデスクトップに付箋として表示させれば、常に目に入るため忘れにくくなります。また、クラウド同期が可能なメモアプリを使えば、複数のデバイスで同じ情報を共有できるため、どこでもアクセスが可能となります。
業務効率化のデメリット
業務効率化には多くのメリットがあるものの、注意すべきデメリットも存在します。
手間やコストの増加
新しいツールやシステムの導入には初期投資が避けられません。また、新しいシステムやプロセスに従業員が新しいプロセスに適応するまでには時間がかかりますし、従業員に対する教育やトレーニングも不可欠です。予想以上に手間やコストが増え、業務が一時的に滞るリスクも考慮する必要があります。
創造的な仕事の減少
効率化の追求が過度になると、従業員が創造的な業務に取り組む機会が減少する恐れがあります。メールの処理が自動化されたとしても、人間の判断や感性を完全に代替することは困難です。効率化が進むと成果が数値にのみ集中し、質の向上につながらないリスクも考えられます。
このような課題を考慮しながら、業務改善を進める際にはバランスを保つことが重要です。
まとめ
業務効率化とは、業務プロセスを見直し、無駄やムラを削減し、効率的に業務を進めるための方法です。少子高齢化社会の加速により、業務効率の向上は一層重要になっています。
効率化を達成するためには、システムの導入が効果的です。例えば、ERPを使用すると、リアルタイムでデータを可視化し、迅速な意思決定が可能になります。また、RPAなどの自動化サービスを活用することで、時間と経費の削減が実現できます。これらのツールやシステムの活用により、コミュニケーションが円滑になり、業務効率が向上します。
効率化の取り組みは生産性向上だけでなく、従業員のモチベーション向上にも繋がり企業全体の成長に寄与します。
当社では、プロジェクト管理に特化したクラウドERPシステム「MA-EYES」やRPA「WinActor」など、幅広い業務効率化を支援するツールやサービスを紹介しています。業務効率化を検討している企業様は最適なものを紹介させていただきます。お気軽にご相談ください。
WinActorはNTTアドバンステクノロジの登録商標です。
記載の社名・製品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。