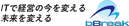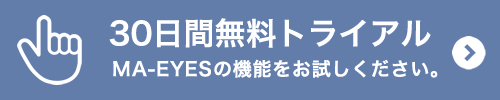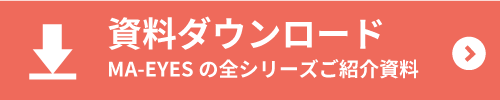システムリプレイスとは、企業が使用している現行のITシステムやソフトウェアを新しいものに交換することを指します。急速に進化するIT技術の中で、企業は業務効率の向上や事業拡大のために、定期的なシステムの見直しとリプレイスを行うことが求められます。 本記事では、システムリプレイスの意味や目的、具体的な進め方や、適切な移行方法、さらに成功のための重要なポイントについて詳しく解説します。
システムリプレイスとは?
リプレイスという言葉には「交換する」という意味が含まれています。システムリプレイスとは、上述した通り、企業が使っている古いITシステムを新しいものに取り替えることを意味します。現代のデジタル化の進展により、業務プロセスや会社の組織を変革するDX(デジタルトランスフォーメーション)が進行中です。また、現行のシステムの老朽化や保守サポートが切れるなどの理由でシステムリプレイスを検討している場合もあるでしょう。
このような背景から、多くの企業がシステムリプレイスを進めています。システムを最新のものにリプレイスすることで、業務効率を向上させ、競争力を高めることが期待できます。
リプレイスとマイグレーションの違い
リプレイスと混同されがちな「マイグレーション」という言葉があります。マイグレーションとは「移動」や「移転」を意味し、現行システムやデータを新しい環境に移行することを指します。例えば、システムマイグレーションは、オンプレミスのシステムをクラウド環境に移行することなどを指します。リプレイスとマイグレーションの違いは、リプレイスはシステム全体の交換を意味し、マイグレーションはシステムやデータの移行を含む広義の概念として理解されます。
システムリプレイスを実施する周期
システムリプレイスの実施期間には明確なルールはありませんが、一般的には5年程度を目安に行うことが推奨されます。これは国税庁が定めるソフトウェアの耐用年数が5年であることが一つの理由です。この期間を過ぎると、システムのパフォーマンスやセキュリティが低下し、業務に支障をきたす可能性が高まります。
また、企業のビジネスプロセスの変化で現行システムと業務管理が乖離している、従業員の不満などが見受けられるなどの場合には、早めのリプレイスを検討することが望ましいです。定期的な現場のヒアリングも併せて行うと良いでしょう。
システムリプレイスの目的
システムリプレイスの目的は主に以下のようなものが挙げられます。
- 上場などを見据え、内部統制を強化するため
- 老朽化したシステムを更新し、パフォーマンスやセキュリティの問題に対応するため
- 技術者の減少に備えるため
- ビッグデータやAIなどの最新技術に対応するため
これらの目的は「攻めの投資」と「守りの投資」に分類されます。攻めの投資はAIやIoTなどのトレンドに対応し、新たなビジネスチャンスを掴むためのもので、守りの投資は社内の課題を解決するためのものです。例えば、新しいビジネスモデルに対応するためのシステム導入は攻めの投資です。一方、古くなったシステムを定期的にリプレイスして問題を未然に防ぐことは守りの投資です。
攻めの投資
攻めの投資とは、企業が今後の経営戦略に基づいて新しいシステムを導入することを指します。近年、オンラインビジネスの拡大やテレワークの普及に伴い、多様なITシステムの利用が求められています。経済産業省もデジタル技術を活用する「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の重要性を提示しています。DXを推進するためには、システムリプレイスを通じて先進的な技術を取り入れ、積極的な投資を行う必要があります。これにより、新たなビジネスチャンスを獲得し、競争が激しい市場での優位性を確保することが可能になります。
守りの投資
守りの投資とは、企業が既存のシステムの老朽化や技術者の減少など、現行システムの問題に対応するためにシステムリプレイスを行うことです。古いシステムを放置することは、運用や保守が難しくなるリスクを伴います。特に長期間使用している独自の社内システムは、管理やメンテナンスが難しいケースが多いです。また、古い技術に精通した技術者が退職したり、減少したりすることで、問題がさらに深刻化します。そのため、定期的にシステムリプレイスを行い、最新技術に対応できるシステムを維持することが重要です。これにより、事業の継続性を確保し、運用コストやリスクを最小限に抑えることが可能となります。
システムリプレイスの進め方
システムリプレイスの進め方には、効果的にプロジェクトを進めるための重要なポイントがいくつかあります。ここでは、具体的な7つのステップをご紹介します。
①プロジェクトチームの立ち上げ
システムリプレイスは、情報システム部門だけでなく、システムを利用する各部門の協力が必要です。各部門から担当者を選出し、プロジェクトチームを結成します。その際、以下の役割を明確に定めておくことが重要です。
- 予算の確保と管理を担う担当者
- 技術的な検討をする担当者
- 現場でのシステム利用を検討する担当者
- プロジェクト全体をまとめるリーダー
このように明確な役割分担をすることで、プロジェクトの進行がスムーズになります。
②要件の洗い出し
次に行うべきは、システムに求める機能や性能を明確にすることです。現行システムで実現できている機能と、将来的に必要となる機能を洗い出します。プロジェクトメンバーと現場の社員が協力し、現状の課題を洗い出し、次にどのようなシステムが理想的かを共有します。これにより、技術者に対しても具体的な要求を伝えることができ、納得のいくシステムの構築が可能になります。
③スケジュールの決定
要件が整理されたら、システムリプレイスのための移行計画を作成します。ここでは、移行期間や移行データの範囲を明確にしておくことが重要です。各部署や担当者との間で認識の相違が生じないよう、詳細なスケジュールと計画を共有します。特に予算に関しては、複数の開発会社から見積もりを取り、最も適したものを選定することが推奨されます。
④予算の確保
スケジュールと計画が作成されたら、それに基づいて予算を確保します。予算確保は社内フローに従い、必要な稟議などを経て承認を得ます。確保された予算は、計画に基づいて適切に管理される必要があります。
⑤ベンダーによるシステム開発
次のステップは、ベンダーによるシステム開発です。開発工程は、以下の順に進められます。
要件定義→システム設計→プログラミング→テスト
要件定義では、システムに求められる機能や性能を明確にし、設計とプログラミングに進みます。開発の各段階で、プロジェクトチームとベンダーは綿密にコミュニケーションを取り、進捗を確認します。最終的にテストを行い、システムが想定通りに動作するかを確認します。
⑥移行テスト(移行リハーサル)の実施
システム移行の前に、移行テスト(リハーサル)を行います。これは、実際の移行時に問題が発生しないようにするための重要なステップです。移行テストでは、移行プロセス全体をシミュレートし、潜在的な問題を洗い出します。この段階でトラブル対策を講じておけば、実際の移行時にもスムーズに対応が可能になります。
⑦移行の実施
移行テストが成功した後、実際のシステム移行を行います。移行後は、旧システムと新システム間でデータの整合性を確認します。また、ユーザーが新システムをスムーズに利用できるよう、必要なサポートを提供することが大切です。移行が完了し、全ての機能が正常に動作することを確認したら、システムリプレイスは完了です。
4つのシステムリプレイス方式
システムリプレイスの進め方には、4つの移行方式があります。企業のシステムや予算に合わせて、最適な方式を選択することが重要です。それぞれの方式には特長とリスクがあるため、正しい理解が必要です。
一括移行方式(一斉移行方式)
一括移行方式(ビッグバン方式)とは、古いシステムを停止して、新しいシステムに一括で置き換える方法です。週末や連休などの影響が出にくい期間にシステムの入れ替えを行う方法が一般的です。
この方式は、既存システムと新システムの連携などが不要なため、時間や費用などのコスト削減でき、事業スピードを速めることができます。しかし、万が一新しいシステムに問題が発生した場合に業務が止まってしまうなどの危険性があることや、導入時には気づけなかった課題が後から出てくるなど、リスクが大きいのも事実です。
短期間で費用を抑えて移行したい場合や、すぐに新システムを稼働させたい場合は一括移行方式が適していますが、失敗のリスクも併せて考慮する必要があります。
順次移行方式(段階移行方式)
順次移行方式(段階移行方式)は、古いシステムから新しいシステムに段階的に移行する方法です。この方法では、各段階で問題が発生しても柔軟に対応でき、次の段階でリプレイスする際に改善が可能です。新システムに不具合があっても停止するのは一部分のみなのでリスクを低減できます。また、場合によってはプロジェクトの方向性を再検討するなども可能です。ただし、一時的に旧システムと新システムが共存する期間が発生するため、連携の必要があるなど運用が複雑になることがデメリットです。
この方式は、大規模プロジェクトや新旧システムの共存が可能な場合に適しており、計画をフェーズに分けて具体的に進めることで成功率を高められます。
並行移行方式
並行移行方式(パラレル方式)は、新旧のシステムを一定期間同時に稼働させる方法です。新しいシステムが安定するまで古いシステムを維持し、データを分析・比較しながら最終的に古いシステムを廃止します。この方式は万が一新システムに不具合があっても業務が止まらず安全性が高い点が最大のメリットです。しかし、2つのシステムを同時に運用するため、二重入力が発生し大きなコストがかかるというデメリットもあります。
場所を選ばずリアルタイムに正確な数字が確認できるため、生産性が向上し、業務効率も改善されます。
並行移行方式は、新システム移行のリスクを最小限に抑えたい場合に適しており、金融機関や医療機関など、データの正確性と信頼性が非常に重要な業界でのシステムリプレイスに向いています。
パイロット移行方式
パイロット移行方式は、新しいシステムを限られた範囲やグループで先行導入し、その結果を評価しながら全体に展開する方法です。この方式を採用することで、実際の運用環境での新システムの性能や問題点を把握し、正式導入するか否かの判断が可能です。しかし、試験段階から多くの手間がかかり、正式導入までに時間がかかるため、一括移行方式のようなスピード感はありません。
パイロット移行方式は、新システムが従来システムと大幅に異なり、未知の要素を多く含む場合に効果的です。新技術導入を目指すIT企業や、新しいビジネスモデルを試みるスタートアップ企業に特に向いています。
システムリプレイスを失敗しないためのポイント
システムリプレイスを成功させるためには、どの移行方式を選ぶかだけでなく、共通して押さえるべきいくつかのポイントがあります。企業の規模や課題に応じて適切な方式を選ぶことは重要ですが、以下のポイントをしっかりと押さえてプロジェクトを進めることで、成功の確率が高まります。
システムリプレイスの目的を明確にする
システムリプレイスをスムーズに進めるためには、まず初めに目的を明確にしておくことが重要です。これにより、実際に検討を進めるときにスムーズに話が進められ、プロジェクトが成功する可能性も高くなります。
経営層や情報システムの担当者だけでなく、実際にシステムを利用する現場の方々や管理職の方々にも、システムリプレイスを行う目的について共通の認識をもってもらえるようにしましょう。
要件定義をしっかり行う
要件定義はシステムリプレイスの最も重要な工程の一つです。新規構築と比較して難易度が高く、企画段階や要件定義での課題認識が不十分だと、後の工程で問題が表面化します。例えば、要件定義に「現行踏襲」という曖昧な仕様で進めると、プロジェクト進行中に仕様の抜け漏れが判明し、リプレイスの遅延や稼働後にトラブルが発生する恐れがあります。要件定義をしっかりと行うために、現状分析を踏まえて再構築の課題を出し尽くし、新システムに必要な機能が過不足なく備わっているかをチェックします。また、課題と対応策を経営層に共有し、経営層が課題を認識して投資判断を行うことも必要です。
要件定義は現場の方にも参加してもらう
要件定義を行う際には、実際にシステムを利用している現場のメンバーも参加させることが重要です。現場の意見を取り入れることで、システムの使い勝手や課題を早期に解決できます。例えば、現場では手作業で補完されている業務がある場合、それがシステム設計に反映されていなければ、新システムでも同じ問題が続いてしまいます。そのため、現場のメンバーを上流工程から参加させることで、業務に必要な機能を漏れなくシステムに組み込むことができます。
経営層にもリスクを認識してもらう
システムリプレイスには多くのリスクが伴います。要件定義や上流工程が曖昧であったり、関係者間で統一されていないと、後の開発やテストの段階で問題が表面化し、遅延やトラブルが発生する可能性があります。そのため、経営層にリプレイスの難しさやリスクを理解してもらい、適切な期間や予算の確保を依頼することが重要です。適正な資金と期間があれば、問題発生時にも迅速に対応でき、プロジェクトの成功率が高まります。
余裕をもったスケジュールを立てる
プロジェクトのスケジュール管理も重要な要素です。タスクを細分化し、リスクを想定した上で余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。また、システムリプレイスの直接的なタスクだけでなく、新システム導入に向けた社内周知や教育、問い合わせ窓口の設置などの間接的なタスクも整理することで、スムーズな導入を実現できます。
既存システムとの連携ができるか確認する
現行システムが他のシステムと連携している場合、新システムでも連携が可能かどうかを事前に確認する必要があります。システム間の連携について整理し、開発会社に伝えることで、予想外の問題を避けられます。現行システムと連携しているシステムや、今後連携を予定しているシステムについても、しっかりと確認し計画を策定します。「リプレイス後も連携できるだろう」と安易に考えず、事前の確認と共有を徹底することが重要です。
信頼できるベンダーを選定する
システムリプレイスには幅広い知識と技術が必要です。自社で進めることが難しい場合には、信頼できるベンダーに依頼しましょう。ベンダーからの提案により、自社で気づかなかった課題や最適なシステム案が見つかることもあります。ただし、ベンダーに丸投げせず、社内で課題とゴールを明確にした上で依頼することが重要です。要件定義の段階からベンダーと緊密に協力し、最適なソリューションを見つけ出しましょう。
システムの停止について確認する
システムリプレイスの方式によっては、一時的にシステムの稼働を停止する必要がある場合があります。その場合、どの部門にどのような影響が出るかを事前に把握しておくことが重要です。システム停止による業務の滞りや、他の業務への影響を最小限に抑えるために、リスクと対応方法を検討する必要があります。特に受注システムなど、社外とも関連があるシステムでは、停止期間中の売り上げへの影響も考慮し、適切な対応策を講じることが求められます。
まとめ
システムを新たなものに置き換える、いわゆるシステムリプレイスは、新規のシステム構築に比べて難易度が高くなることが多く、その結果、コストの増加やスケジュールの遅延などのリスクが伴います。リプレイスには主に4つの方式が存在し、企業の現行業務の規模や状況に応じて最適な方式を選択することが重要です。基本的な進め方として、まず関係部門と協力してプロジェクトチームを結成し、その後詳細な移行計画を策定します。移行の際には、実際の運用状況をシミュレートしたリハーサルを念入りに行うことが求められます。
さらに、システムリプレイスのリスクを軽視せず、上流工程から関係部門が積極的に参画することが不可欠です。システム開発会社を含めてリプレイスにおけるリスクを洗い出し、その予防策を明らかにしてから実施することで、プロジェクトの成功確率を高めることができます。
当社ビーブレイクシステムズでは、クラウドERP「MA-EYES(エムエーアイズ)」を提供しています。MA-EYESは標準機能が豊富なため、そのまま利用することも、自由にカスタマイズをすることもできます。導入形態は3種類から選択することができ、どのような規模のお客様にも使っていただける選択肢の多さと柔軟さが特徴です。
導入時や導入後のサポートも豊富なため、安心してご利用いただけます。
システムリプレイスの際は、是非ご検討ください。
記載の社名・製品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。