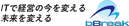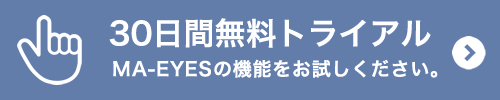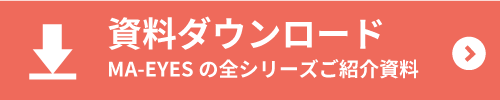「売上は順調なのに、なぜか利益が伸びない」「どのプロジェクトが本当に儲かっているのか見えない」といった悩みを抱えていませんか?
特に、人件費が主体のIT・コンサルティング業界では、製造業とは異なるアプローチでコストを管理する必要があります。
原価管理は、不採算プロジェクトの早期発見から価格設定の最適化、さらにはIPOを見据えた体制構築までを可能にします。
本記事では、この課題を解決するポイントとなる「原価管理」とは何かを定義し、プロジェクト型ビジネスに特化した実践的な手法を解説します。

原価管理がプロジェクト型ビジネスに必須な理由
多くの企業で原価管理は「やらなければならない作業」として後回しにされがちですが、実は利益を最大化するための重要な戦略ツールです。特にITやコンサルティング業では、原価の大半を占める「人件費(労務費)」が不透明になりやすく、適切な原価管理なしに黒字経営を維持することは困難です。
原価管理を行うメリットは次の3つです。
理由1:プロジェクト別の採算性をリアルタイムで把握できる
原価管理を導入することで、「どのプロジェクトにどれだけの費用(主に工数)がかかり、結果としてどれだけの利益を生んだか」という採算性を可視化できます。
そのため「体感では黒字だと思っていた案件が、実は赤字だった」というリスクを防げます。リアルタイムで採算性を追跡できれば、コスト超過の予兆を早期に察知し、リソース投入の調整やクライアントへの交渉など、適切な手を打てるようになります。
理由2:見積・価格設定の精度が上がり、機会損失を防げる
プロジェクト型ビジネスでは、案件ごとに工数や難易度が変わるため、見積もりが非常に難しく、経験や勘に頼りがちです。
原価管理によって過去の類似プロジェクトの「実際にかかった原価」がデータとして蓄積されることで、新しい案件に対する見積もり精度が格段に向上します。原価割れの受注を防ぐだけでなく、高すぎる価格設定による機会損失も回避できるようになります。
理由3:実行可能なコスト改善策を論理的に導き出せる
原価管理の最終目的は、原価を把握して終わりではなく、原価を分析して改善することです。
標準原価(目標)と実際原価(実績)の差異分析を行うことで、「見積もりの甘さ」や「作業効率の悪さ」など原因を特定できます。そのため、「工数入力の効率化」「無駄な会議を減らす」など、具体的な改善策を講じることが可能となります。
原価管理とは?
原価管理とは、「目標とする利益を達成するために(Plan)、原価を計画的に算定し(Do)、統制し(Check)、継続的に改善していく活動(Action)」のことです。
この活動は、計画→実行・計算→差異分析→改善というPDCAサイクルで構成されています。原価管理の成否は、このサイクルを継続的に回せるかどうかにかかっています。
本章では原価管理の目的、原価計算との違いなどの基礎について解説します。
原価計算は原価管理の「手段」:計算と改善の役割の違い
原価管理とよく混同されがちな用語に「原価計算」があります。原価計算とは、製品やサービスにかかった費用を正確に算定することであり、財務会計や税務申告に必要な数値を出すための作業(義務)です。原価管理のプロセスにおける「Do(実行・計算)」の一部を担います。
この2つの決定的な違いは、原価計算が「原価を把握すること」を目的とするのに対し、原価管理は「把握した原価をもとに改善すること」を目的とすることです。つまり、原価計算は原価管理を推進するための「手段」であり、原価管理こそが「目的」なのです。
原価管理の具体的な目的(予算統制 / 意思決定 / 価格設定 / 業務改善)
原価管理を行う目的は多岐にわたりますが、特にプロジェクト型ビジネスにおいて重要なものを紹介します。
- 予算統制:プロジェクトの実行中に発生するコストを常に目標(予算)を超過しないようにコントロールすること。
- 意思決定の支援:どの事業・プロジェクトにリソースを集中すべきか、採算性の低い事業から撤退すべきかなど、経営の重要な判断を下すための客観的なデータを提供すること。
- 適切な価格設定:過去実績に基づいた正確な原価を把握し、競争力があり、かつ確実に利益が出る適正な販売価格を設定すること。
- 業務改善の推進:原価の無駄や非効率なプロセスを発見し、生産性向上につながる具体的なアクションを現場に促すこと。
プロジェクト型ビジネスにおける原価
製造業では材料費が原価の大部分を占めますが、IT・コンサル業では、社員の工数に換算される労務費が、原価全体の半数以上を占めることが一般的です。この特徴から、プロジェクト型ビジネスの原価管理の成功は、いかに社員の工数実績を正確に把握し、これを金額(労務費)に換算できるかにかかっています。工数管理の精度が、そのまま原価管理の精度に直結すると言えます。
ここではプロジェクト型ビジネスにおける原価の種類について解説します。
直接費(人件費、外注費など)
直接費とは、特定のプロジェクトやサービスに直接的に対応付けて集計できる原価のことです。プロジェクト型ビジネスでは、主に以下のものが該当します。
- 直接労務費(人件費): 開発者やコンサルタントなど、プロジェクトに直接従事したメンバーの工数(時間)と、そのメンバーの時間単価をかけ合わせた費用
- 外注費: プロジェクトの一部を外部のフリーランスや協力会社に委託した場合の費用
- 直接経費: プロジェクト専用に購入したソフトウェアライセンス、特定の移動旅費など
間接費(家賃、共通部門の人件費など)
間接費とは、特定のプロジェクトに直接対応付けられず、複数のプロジェクトや部門で共通して発生する費用のことです。正確な採算性を把握するためには、この間接費を何らかの基準で各プロジェクトに「配賦(はいふ)」する必要があります。
- 間接労務費(間接部門の人件費): 経理、人事、営業など、プロジェクトを直接担当しない部門の社員の人件費
- 間接経費: オフィス家賃、共通で利用する通信費、光熱費、全社共通のシステム利用料など
原価管理を成功させる手順
プロジェクト型ビジネスに特化した、実践的な原価管理の手順を解説します。
①標準原価(目標コスト)の設定:プロジェクトごとの予算の設定
プロジェクトの開始前に、「そのプロジェクトで許容できる理想的な原価(コスト)」を目標として設定します。これが標準原価です。
標準原価は、過去の類似案件の実績データや、業界の標準工数などを参考にしながら、工数・外注費・経費の各項目で具体的な予算額として定義されます。この設定を厳密に行うことが、後の差異分析の基準となり、プロジェクトマネージャーのコスト意識を高めます。
②実際原価の集計:工数実績、外注費、間接費を正確に記録
プロジェクトが実行される中で、実際にかかった費用を実際原価として漏れなく集計します。
具体的には、社員が日々入力する工数実績(誰が、いつ、何に、何時間かけたか)、外注先への支払額、プロジェクト専用の経費精算データなどがこれにあたります。この集計作業には高い正確性とタイムリーさが求められます。特に工数実績は、社員全員の入力の徹底が不可欠です。
③差異分析:標準原価と実際原価のズレから原因を特定
実際原価の集計が終わったら、事前に設定した標準原価との「ズレ(原価差異)」を分析します。
例えば、原価が超過している場合、それは「予定よりも多くの工数を投入した(量的な差異)」のか、「人件費単価が上がった(価格的な差異)」のかといった原因を深掘りします。この分析により、問題が「見積もり段階」にあったのか「実行段階」にあったのかが明確になります。
④改善アクションの実行:PDCAを回す
差異分析の結果に基づき、次期以降のプロジェクトや現行プロジェクトに対して具体的な改善アクションを実行します。
- 例1:量的な差異
→「非効率な作業フロー」が原因であれば、ツールの導入や業務マニュアルの改訂を行う - 例2:見積もりの甘さ
→「工数予測の誤り」が原因であれば、見積もりチェック体制の強化や過去データの再分析を行う
この改善アクションを次のプロジェクト計画に反映させることで、原価管理のPDCAサイクルが回り、組織の収益体質が継続的に強化されていきます。
ITシステム活用のメリット
プロジェクト数や社員が増えれば増えるほど、エクセルや手作業での原価管理は限界を迎えます。特に複雑な間接費の配賦やリアルタイムな状況把握は難しく、これを解決するのが原価管理に特化したITシステム(ERPなど)の活用です。
リアルタイムな原価の把握:月末を待たずに赤字の予兆を検知
エクセル管理の最大の欠点は、データ集計が月末に集中し、「結果が出た時には手遅れ」になってしまうことです。原価管理システムを導入すれば、社員の工数入力が即座に原価計算に反映され、プロジェクトの進捗と採算性をリアルタイムでダッシュボードに表示できます。これにより、目標工数に対して実績工数が何%消化されたかを常時監視でき、赤字プロジェクトの予兆を早期に察知し、即座にマネージャーが手を打てるようになります。
複雑な間接費の配賦:自動化し、効率と正確性を向上させる
プロジェクト型ビジネスにおいても、共通で発生する間接費(家賃、共通部門の人件費など)を各プロジェクトに割り振る配賦(はいふ)作業が必要です。しかし、配賦基準の計算は複雑で、手作業ではミスが発生しやすい領域です。
原価管理システムは、あらかじめ設定された配賦基準(例:売上比、工数比、人員比)に基づいて、間接費を自動でプロジェクトに割り振ります。これにより、経理担当者の作業負担が大幅に軽減され、計算ミスのない正確性の高い原価データを担保できます。
予実管理の徹底:差異分析の時間を短縮
原価管理システムの核となる機能の一つが予実管理です。システム内でプロジェクトごとの予算(標準原価)を登録しておけば、工数実績や経費実績(実際原価)が入力されるたびに、予算に対する進捗率や差異を自動で計算・可視化します。
これにより、担当者は複雑な計算や表の作成に時間を割く必要がなくなり、差異分析という「考える時間」にリソースを集中できるようになります。結果として、PDCAサイクルのスピードが向上します。
IPO・企業成長を見据えた原価管理体制の構築ステップ
成長を志向する企業、特にIPOを視野に入れている企業にとって、原価管理は企業の信頼性と持続性を証明する重要なガバナンス(内部統制)の要素となります。
なぜ成長企業に高度な原価管理が必要なのか:上場審査と投資家への説明責任
上場審査において、企業は継続的に利益を生み出す体質と、その利益が不正なく正確に計算されていることを証明する必要があります。特にプロジェクト型ビジネスでは、売上計上と原価発生のタイミングがずれやすいため、正確な期間損益を計算するための強固な原価管理システム(管理会計)が求められます。
曖昧な原価計算や属人化した管理体制は、審査で厳しくチェックされます。高度な原価管理は、投資家に対し「当社の収益構造は透明で安定している」と説明する信頼の証となるのです。
ステップ1:ルール化(工数入力ルールの策定と徹底)
強固な体制構築には、全社的なルールの整備が必要です。特に人件費の根拠となる工数入力について、「入力対象者」「入力単位(時間単位など)」「入力期限(毎日/毎週)」「承認フロー」を全社員へ共有し、徹底します。ルールが曖昧だとデータも曖昧になり、IPO審査に耐えうる正確性を確保できません。経営層が先頭に立ってルールの遵守を推進することが不可欠です。
ステップ2:システム化(部門間の情報連携と内部統制の担保)
次に進めるべきは「システム化」です。ルール化された工数実績、経費実績、請求データなどをバラバラに管理するのではなく、一元管理できるシステム(ERPなど)を導入します。
システム化により、複数の部門にまたがる情報(営業の見積もり、現場の工数、経理の精算)が自動で連携し、データの一貫性が保たれます。また、データの改ざんを防ぐためのアクセス制限や履歴管理が可能になり、内部統制を担保できます。
ステップ3:戦略化(管理会計レポートの定型化と経営層へのフィードバック)
システム導入が完了したら、原価データを「戦略」に活用するフェーズです。システムから抽出される採算性レポートや差異分析結果を、経営会議や部門会議で定期的に活用する仕組みを定着させます。
原価管理を最適化するMA-EYES
貴社が「プロジェクトの採算が不明瞭」「エクセル管理が限界」といった悩みを抱えているのであれば、プロジェクト型ビジネスに特化して作成されたクラウドERP「MA-EYES」が最適です。MA-EYESは、特に人件費が主体のビジネスモデルにおけるIT、コンサル、広告業の原価管理の課題を解決します。
工数入力から実際原価を自動で集計
プロジェクト型ビジネスの原価計算で最も手間とミスが発生しやすいのが、人件費の計算です。MA-EYESは、社員や外注パートナーが入力する工数の実績情報から支払や請求データを作成します。SESなどの複雑な採算管理も可能です。手作業によるエクセルへの転記や集計が一切不要となり、データ精度が飛躍的に向上します。
柔軟な配賦設定
複雑な間接費の配賦ルールも、MA-EYES内で柔軟に設定・運用できます。「部門別売上比」「稼働時間比」「人員数比」など、貴社の管理会計方針に合わせた多様な配賦基準をシステムに組み込むことができます。これにより、属人化していた配賦作業が自動化され、客観的なプロジェクト別原価を算出することが可能となります。
経営層向けの管理会計レポート
経営層が必要とするのは、細かな経理データではなく、意思決定に直結する分析情報です。MA-EYESは、プロジェクト別、顧客別、部門別といった様々な切り口での採算性レポートを標準搭載しており、経営層はいつでも最新のデータに基づき、「どの事業に投資すべきか」「価格戦略をどう見直すか」といった戦略的な判断を迅速に行うことができます。
豊富な標準機能
MA-EYESはプロジェクト型ビジネスに必須の商談管理、契約管理、請求管理、売上管理など豊富な機能を持ったクラウドERPです。原価から売上・利益まで1つのシステムで管理できるため、部門間の情報連携ミスがなくなり、全社的な業務効率が大幅に改善されます。
MA-EYESのインタビューと事例
MA-EYES原価管理を実現した事例を紹介します。
- 【株式会社ドワンゴ様】様々な配賦パターンに対応するプロジェクト原価管理システムを構築
- 【株式会社リサーチ・アンド・ディベロプメント様】財務会計とプロジェクト原価管理をひとつのシステムで実現
- 【株式会社カジマアイシーティ様】適切な内部統制を維持しつつ業務の効率化と原価管理方法の見直しを実現
まとめ:原価管理は利益を生み出す「攻め」の経営ツール
本記事で解説した通り、原価管理とは、単に費用を計算することではなく、目標利益を達成するために原価を統制し、改善していくための「攻め」の経営管理活動です。特にプロジェクト型ビジネスにおいては、人件費という目に見えにくい原価を正確に把握できるかどうかが、企業の利益と成長を決定づけます。
「エクセルでの管理は限界」「プロジェクトの採算が不明瞭」といった課題がある方はぜひ、クラウドERP「MA-EYES」の導入をご検討ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としております。個別の事案や詳細内容については専門家にご確認ください。
記載の社名・製品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。