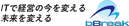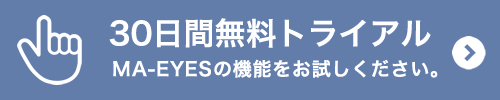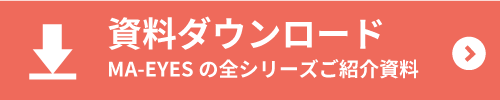購買管理とは、企業が必要とする物品やサービスを適切な価格、数量、品質、納期で調達できるように管理することです。購買プロセス全体を効果的に管理し、最適化することで利益向上やコスト削減に繋がります。
本記事では、購買管理を効率的に進めるための購買管理の5原則についても紹介します。5原則には、品質の維持、適切な価格交渉、確実な納期遵守、必要な数量の確保、内部統制の強化などが含まれ、実践することで企業全体の調達管理が正確かつ効率的に行われます。
さらに、購買管理システムを導入することで得られるメリットも紹介します。
購買管理の目的
購買管理の目的は、必要なものを適切な品質と価格で、必要な時に必要な量だけ購買することです。購買業務は企業の利益に直結し、現場の作業効率にも大きく影響するため、慎重で正確な管理・運用が求められます。購買管理を適切に行うことで、サプライチェーン全体の効率と品質を向上させることができます。
購買管理には、購買計画の策定、仕入先の選定、発注管理、原価確認、納期スケジュール作成といった一連の作業があります。
購買管理においては、モノを買うことだけに目を向けるのではなく、不必要なモノを買わせないという観点も重要です。これにより経費節減と効率的な資源活用が可能となります。
「調達管理」との違い
「購買管理」と「調達管理」はしばしば同義語として使用されますが、実際には異なる管理領域を指します。
購買管理は、”ものを買うこと”すなわち発注から受け取りまでの一連のプロセスを管理する業務に焦点を当てています。
一方、調達管理は「もの」を買うだけでなく、「人」や「金」などを含む”生産に必要なもの”を調達することを指します。
調達管理は、購入以外の方法であるレンタルやリースによる調達も含みます。また、小売工程までの管理、人材や設備などの生産能力に関わる部分の整備など、調達全般を管理する業務を指します。
購買管理は調達管理に含まれていますが、特に購買に関わる部分を購買管理と言います。
購買管理の5つの原則
購買管理業務の効率向上やコスト削減、品質の向上を実現するために購買管理の基礎とも言える「購買管理の5原則」を押さえましょう。購買管理の5原則とは、以下の5項目です。
- ①適切な品質の確保
- ②適切な数量の決定・確保
- ③適切な納期の設定・確保
- ④適切な価格の決定
- ⑤適切な取引先の選定
それぞれ解説します。
①適切な品質の確保
納品物の品質を確保することは顧客満足度を維持するためにも重要です。高品質な商品や部品を選ぶことで、最終製品の品質向上につながります。
適切な品質な製品を安定して供給するためには、まず会社の品質基準を設定し、仕入れ先と共有することが求められます。
購買品が規定の品質基準を満たしているか定期的に検査し、技術力や品質に見合った価格の資材・原料を選定します。さらに、納品後に品質に問題が発生した場合は迅速で適切なクレーム対応を行い、再発防止策を講じることが重要です。
②適切な数量の決定・確保
必要な量を把握し、それに基づいた発注を行うことは在庫管理を効率化するうえで必要です。
適切な数量を決定するための具体的な方法として、まず、需要分析が必要です。過去の販売データや市場動向を詳細に分析することで、適切な購買数量を予測します。これにより、在庫不足や過剰在庫のリスクが軽減されます。
また、注文ロットの最適化も行いましょう。経済的注文量(EOQ)を計算し、発注ごとのコストと在庫コストを最小化することで、無駄なコストを削減できる仕組みを作り上げます。
在庫管理システムの導入もオススメです。現在の在庫状況を常に把握できるシステムを導入することで、過剰在庫や在庫不足を防ぎ、効率的な在庫管理が可能となります。
③適切な納期の設定・確保
供給遅延を防ぐためにも適切な納期の設定が必要です。納期は製品やサービスの供給に直接影響し、他の購買業務や製造業務にも影響を与えます。 発注リードタイム(発注から納品までの時間)を確認し、適切な納期の確保を常に意識しておくことが重要です。
仕入れ先とのコミュニケーションも重要です。納期に関する情報を密に共有し、納期遅延などのリスクを最小限に抑えましょう。自社と仕入れ先の指揮系統や緊急時の対応について事前に話し合い、効率的な業務フローを確立することが、適切な納期の確保につながります。
契約書に納期に関するペナルティや保証条件を明記し、万が一のトラブルを未然に防ぐことも重要です。
④適切な価格の決定
購買業務において、適切な価格での仕入れは企業の利益に直結する重要な要素です。
まずは市場価格や競合他社の価格を詳細に調査し、適正な価格レンジを把握しましょう。市場での位置付けを理解することで、適切な判断が可能になります。
購入品のコスト構造を詳細に分析し、材料費、人件費、輸送費などの内訳を把握することで、適正価格を試算します。これにより品質を損なうことなくコスト削減を図ることが可能です。
仕入れ先との価格交渉も、購買業務において必要なスキルです。長期的な取引関係や大量購買を活用して有利な条件を引き出し、最適なコストを実現しましょう。
購買業務では仕入額の過剰な削減が品質低下を招くリスクもあるため、原価低減活動と品質維持のバランスを取ることが求められます。慎重に価格を決定し、企業の収益向上を目指しましょう。
⑤適切な取引先の選定
信頼性の高い取引先(サプライヤー)を選ぶことで供給の安定とコスト効率、高品質な製品が確保できます。複数の仕入れ先から見積もりを取り、最適な取引先を選定します。
取引の前に、必ず取引先の与信管理を徹底しましょう。具体的には財務状況や過去の取引実績、他企業からの評判を確認するなどです。信用や能力に問題がある場合、仕入プロセスの滞りや生産計画の狂い、発注ミス、倒産リスク、違法なルートからの仕入れ、情報漏洩などのリスクが考えられます。
また、災害や不測の事態に備え、バックアップの仕入れ先を確保しましょう。これにより、納期や数量面でも安定供給を確保し、リスクを最小限に抑えられます。
適切な取引先の選定は、その他の購買管理の5原則(納期、数量、価格、品質)にも大きく影響します。
購買管理のメリット
購買管理の体制を見直すことで以下のようなメリットがあります。
原価低減による利益向上
購買管理を行うことで原価を抑えることができるため、企業の利益向上を実現できます。
複数の仕入れ先を比較し、価格交渉を行うことで、商品やサービスを作成する際の原材料や資材の調達コストを最適化し、より低コストで高品質の材料を入手できます。また、長期的な契約を結ぶことで、安定した価格での供給も期待できます。これにより、製品のコストを抑えつつ、利益率を向上させることができます。
生産効率の向上
購買管理の適切な運用は、生産効率の向上に直結します。必要な材料がタイムリーに供給されることで、製造ラインの停滞を防ぎ、スムーズな生産が実現します。
購買データを詳細に分析することで、消耗品の使用傾向を把握し、無駄のない購買計画を策定できます。これは生産部門のみならず、経理や事務などのバックオフィスにおいても有効です。コピー機のトナーや文房具の備品切れを防ぐことで、業務の生産性を維持しながら効率的な運営が可能となります。
また、発注ミスや在庫管理ミスの軽減が可能となり、結果としてリードタイムが短縮され、入荷・発注作業がスムーズに行われます。それに伴い、購買以外の製造部門などの作業効率も向上します。
従業員による不正の防止
企業の購買管理は社内の規律を守ることに繋がり内部統制が強化します。
承認フローを明確にし、複数の担当者によるチェック機能を導入するなど、厳密な購買管理を行うことで、購買プロセスの透明性を高め、従業員による不正のリスクを軽減できます。
また、購買システムを導入することで、すべての取引履歴を記録・監視し、不正の兆候を早期に発見することが可能です。これにより、備品と私物の同時購入や運営資金の私用利用などの不正行為を未然に防ぐことができ、従業員のコンプライアンス意識が向上し、不正防止が期待できます。
購買管理の主な流れ
購買業務の流れは、購買計画から始まり、仕入れ先の選定、契約締結、発注、納品、検品、そして支払に至ります。購買管理を最適化するには、各ステップでの具体的な業務フローを確立することが大切です。また、プロセスの改善点を見つけ、適切なシステムを導入することで、さらに効率化と管理の精度向上が期待できます。 順番に説明します。
1.購買計画の決定
まず最初にやることは購買計画の決定です。生産計画に基づき、必要な物資やサービスの種類、数量、購入時期、予算を詳細に確認した上で計画を立案します。長期的な視点を持って、企業全体の戦略に合わせて計画を立てましょう。具体的な購買計画を作成することで、予期せぬコスト削減や供給の遅れなどのリスクを最小限に抑えることができます。購買計画を適切に決定することで、業務フローの効率化にも繋がります。
2.仕入れ先の選定
続いて、いくつかの候補から信頼できる仕入れ先を選定します。販売価格、資材や原料、仕入れルート、業績、評判などを総合的に評価します。特に品質管理や納期の遵守状況も重要な評価ポイントとなり、購買業務を円滑に進めるための選定基準とします。
3.見積もり依頼
選定した各仕入れ先に見積もり依頼を行います。この段階で、取引経費や資材・原料の販売価格、納期、提供されるサービスの詳細な見積もりを取得します。また、自社の求める品質基準や価格基準を満たしているかも確認しましょう。
このとき、相見積もりをもらうことで価格競争によるコスト削減が期待できます。各仕入れ先からの見積もりをもらったら比較検討します。その際は価格だけでなく、納期や品質、アフターサービスなど広い視点で評価し、最適な仕入れ先を選定します。
4.契約・発注
比較検討の結果に基づき、契約を締結します。契約書には価格、納期、品質基準、支払い条件などが明記されます。契約を締結したら、実際の発注業務に移行します。発注の前に倉庫スペースや生産状況、在庫数を確認して適切な管理を行いましょう。
5.納期・状況確認
発注後は、生産計画やスケジュールに支障が出ないように、納期や生産状況の定期確認が必要です。仕入れ先の出荷状況を確認し、納品が遅れる場合には迅速に対策を講じることが求められます。また、遅延や不具合が発生した場合には、仕入れ先とのコミュニケーションなど速やかに問題を解決するために対応が必要です。
6.受け取り・品質チェック
納品された物資やサービスについては、その種類、数量、品質、消費期限、破損していないかなどを細かく検収・検査します。この際、設定された品質基準に基づいて厳格にチェックし、不適合な項目が発見された場合は速やかに仕入れ先へ連絡し、必要な対応を依頼します。例えば、数量が不足している場合や品質に問題がある場合は即座に報告し、適切な交換や修正を求めましょう。このような徹底した品質チェックを行うことで、製品の品質を維持します。
7.保管・移動
受け取った物資は適切に保管しましょう。必要に応じて物資を現場へ発送し、在庫として管理します。保管方法や移動は在庫管理と関連しており、こうしたプロセスを効率化することで企業のコスト削減や業務のスムーズな遂行に貢献します。
システムを導入することで、在庫管理の精度が向上し、リアルタイムでデータ取得が可能になります。これにより、不必要な在庫の削減や欠品の防止が図れ、購買管理全体の改善が期待できます。
8.支払い
仕入れ先から請求書が届いたら、請求内容を確認し、問題がなければ規定の期日までに入金手続きを行いましょう。請求内容を確認し、必要な場合は仕入れ先に確認を取ります。契約条件に基づいて迅速かつ正確に対応することが重要です。不備のない入金は取引先との信頼関係を築き関係強化につながります。
購買管理における内部統制の重要さ
内部統制とは、企業内で不正や人的ミスが起こらないように組織的に管理する仕組みです。具体的には、監視体制の整備、業務フローの見直し、ルールの明確化などを行います。特に購買管理では、不正などが起こりやすいため、購買管理における内部統制の強化が不可欠です。内部統制を強化することで、購買プロセスの透明性が確保され、リスクの低減、品質の維持、不正の防止が図られます。
また、購買管理の分野だけでなく、業務の効率化、財務報告の正確性確保、法令遵守の徹底、資産の保全といった多岐にわたる目的に貢献します。
内部統制実現に向けて
内部統制を実現するために、購買基準と購買管理業務のルールを決める必要があります。それぞれ説明します。
購買基準を決める
購買基準とは、購買品の仕様、仕入れ先の選定基準、取引基準、購買条件などを示します。この基準を明確化することで、客観的な判断ができる体制を整え、購買業務の効率と信頼性を向上させることができます。
購買管理業務のルールを決める
購買活動を健全に運営するために、具体的な業務フローと承認ルールの策定が必要です。
例えば、発注から納品までの各ステップで誰がどの業務を担当するのか、承認基準を明確にすることが求められます。これにより、ミスや不正の発生を防ぎ、業務の標準化と効率化が実現します。
さらに、購買管理システムの導入を検討することで、購買業務全体の可視化や追跡が可能となります。資材の発注・納入・支払状態の管理、納品書や請求書の電子化、在庫管理など、システムは一元的な管理をサポートします。購買管理システムの活用により、業務の透明化と効率化が進み、ヒューマンエラーの防止にもつながります。
内容統制実施のポイント
購買管理に関する内部統制を構築するためのポイントを解説します。
役割を1人に任せず分担する
購買業務を特定の個人に集中させると、ミスや不正のリスクが高まります。そのため、業務を明確に分担し、複数の担当者がチェックし合う体制を構築します。
たとえば、発注担当と支払担当、在庫管理担当と検収担当を分ける方法があります。役割分担により、相互監視が強化され、透明性が保たれます。
また、購買業務が属人化すると、担当者の欠勤や退職、休暇で業務が停止するリスクもあります。また、個人の裁量に依存するとブラックボックス化し、不正やミスが発見しにくくなる可能性もあります。業務プロセスごとに適した人材を割り当て、役割を分担することで、これらのリスクも大幅に軽減できます。
購買担当者を定期的に変更する
購買担当者は長期間同じ業務を担当すると取引先との関係が深くなりすぎ、不正行為や癒着のリスクが高まります。これを防ぐために一定期間ごとに担当者を変更することが推奨されます。
担当者のローテーションは、不正の抑止効果が期待できるだけでなく、新鮮な視点をもたらす機会にもなります。また、引き継ぎをしっかり行うことで業務の遅延を防ぎ、スムーズな運営を維持することが可能です。
不正チェックの仕組みつくり
不正を未然に防ぐためには、定期的な監査やチェックなどの堅固な仕組み構築が欠かせません。
特に購買業務では、仕入れ先との関係構築や資金管理が重要であるため、担当者と仕入れ先の癒着を防ぐ必要があります。チェック体制を強化するために、内部監査の定期実施や監査機能の導入などの第三者による監査や、複数人承認を導入しましょう。
システムを活用して機械的にチェックすることも有効です。これにより、不正行為の早期発見と迅速な対応が可能となります。
購買業務効率化のポイント
購買管理は多くのステークホルダーが関与し、業務が複雑化しがちです。購買管理を効率的に行うためのポイントは以下です。
購買方法を統一する
企業の購買方法は多岐にわたりますが、各部署や担当者が個人の裁量で購買管理を行っていると、重複発注や価格のばらつきが発生しやすくなります。これを防ぐために、購買ポリシーやルールを明確し、全社的に統一した購買方法を適用することが必要です。
購買フローをマニュアル化し、社内で共有することで、担当者が休んでいる時に業務が滞るなどの問題も解消されます。誰が担当しても同じ品質で遅れなく商品を購入できるようになります。
システム導入による自動化も効果的です。業務フローの設定や引き継ぎもスムーズになります。購買管理のフローを統一するだけでなく、人的ミスを減らすことができ、確認等に要する時間も短縮できるため、全社的な業務効率の向上が期待されます。
購買データを共有する
購買業務の効率化には購買データの一元管理も大切です。全社的なデータの可視化により、過去の購買履歴や現在の在庫状況、取引先ごとの条件をリアルタイムで把握できます。これにより、購買の意思決定が迅速かつ正確に行われます。
例えば、クラウドベースの購買管理システムを導入することで、全てのデータを一元管理し、社内の関係者が必要な情報にいつでもアクセスできるようにします。購買データの分析を通じて、コスト削減の余地や改善点を見つけることが可能です。
また、自動的に発注履歴や在庫データを更新する機能を活用すれば、手作業によるミスやデータ入力の時間を大幅に削減できます。
購買管理の情報共有を日頃から行うことで、ミスや遅延が減少し、取引先との交渉力も向上します。
購買管理システム導入のメリット
企業の購買活動を円滑に進めるためには購買管理システムの導入が効果的です。システムを導入することで、購買から仕入れ、請求までの管理を自動化し、時間と労力の節約を図ることができます。
購買管理システム活用の具体的なメリットについて詳しく解説します。
過去のデータを確認できる
購買管理システムを導入すると、過去の購買データを一元管理でき、迅速かつ容易に取引履歴や調達コストを確認できます。特に、多数の取引先や商品を扱う企業にとって、過去データを蓄積し、有効活用できるため大きなメリットとなります。
再発注時に参考データを簡単に取得できるため、長期的な取引実績を持つ仕入先に過去のデータを示すことで、価格交渉や仕入先選定が有利に進みます。
ペーパーレス化を実現
購買管理システムを導入することで、ペーパーレス化を迅速に実現できます。購買業務における注文書や支払書などの書類を電子化することで、紙代不要によるコスト削減が期待できます。
また、デジタルデータで保管することで、保管スペースや文書管理の手間を大幅に軽減し、迅速な情報検索と取得が可能になります。
一方、取引先企業が紙ベースの書類のみを受け付ける場合、システム導入前に契約内容の整理や見直しが必要です。また、請求書や契約書のデータ保存には電子スタンプや電子署名の付与も重要です。したがって、購買管理システム選定時には、電子スタンプや電子署名対応の確認、紙書類と電子書類の併用可能性など、自社業務に合致するかを慎重に確認することが重要です。
リアルタイムに情報共有可能
システムを通じて購買情報をリアルタイムに共有することで、部門間の連携が大幅に向上します。例えば、在庫状況や発注ステータスなどの情報を即座に共有することで、購買部門と生産部門の連携が強化され、在庫不足や過剰在庫のリスクを効果的に回避できます。
この結果、関連部署へのタイムリーな報告が促進され、迅速で的確な意思決定が実現されます。
不正やミスを防止
購買管理システムは承認フローやログ管理機能を搭載しており、不正取引やミスを事前に防止する効果があります。例えば、一定金額を超える発注には上司の承認を必須とするなどの機能が備わっているものもあります。
誰が、いつ、どこから、何を購入しているかといった購買業務のフローを可視化することで、人的ミスや不正行為の早期発見が可能となります。また、システムログを定期的に監査することで不正行為の抑制が期待できます。企業のコンプライアンス強化が実現し、信頼性の向上にも寄与します。
MA-EYESの購買管理
当社ではMA-EYES(エムエーアイズ)というERPシステムを提供しています。MA-EYESはプロジェクト管理に特化したシステムで、
“人件費”を主な原価としている企業向けとなっています。
MA-EYESの購買管理は、プロジェクトに紐づく外注費や業務で利用するPCなどの購買を管理することができます。
SESの購買管理
外注の購買は、この業務に対していくらと金額が決まっている場合もありますが、特にITの分野だとSESといって、かかった時間に伴い支払う場合もあります。
その際に精算幅といって、月額単価や上限時間、下限時間が決まっており、上限時間を超えた場合に超過分に対していくら、下限時間を下回った場合に控除時間に対していくらと決めて支払いをします。
MA-EYESでは、外注の月額単価、超過、控除、上限時間、下限時間をそれぞれプロジェクトごとに設定することができ、アサイン時間より自動で計算し支払い金額を算出することができます。
購買情報を元に請求データを作成することも可能です。
業務のシステム化を検討している方は、資料ダウンロードなどもございますので是非ご利用ください。
まとめ
本記事では、購買管理の基本から具体的な業務フロー、改善方法、さらにシステム導入のメリットまでを詳細に解説しました。
購買管理をこれから始めようと思っている方の一助となれば幸いです。