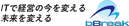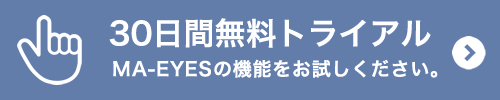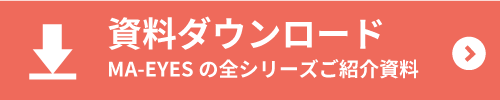4. SLAとは
こちらはビーブレイク業務システム研究室です。
今回は「SLA」について。
最近、システム導入の際にSLAという言葉をよく聞きますが、SLAとは何なのでしょうか?
SLAとはサービスレベル・アグリーメント(Service Level Agreement)のことで、システムを提供する側と利用する側とで交わされる情報システムのサービスレベルに関する契約のことです。
と言われてもピンときませんので、具体的に考えてみましょう。
例えば…
システム利用者は、システムを毎日何時でも使えると思っている。システム提供者は、バックアップやメンテナンスのため夜間や休日は利用者へのシステム提供を停止することを想定している。このケースの場合、システムの利用者と提供者の間でシステムの利用時間についてギャップが生じている状態です。
システムを使うようになってこのギャップが発覚したとするとどうなると思いますか?利用時間によっては利用者がシステムを使おうとしたら使えないという状況になり、現場が混乱してしまうかもしれません。
もし両者間でシステムの利用時間について予め決めておけば、このような混乱は起きないでしょう。
SLAではこのようなシステムのサービスレベルを合意すること(つまり利用者と提供者の間でシステムのサービスレベルのギャップを埋めること)が目的で作成されます。
ではSLAは実際どのような内容がもりこまれるのか、いくつか例を挙げてみます。
- サービスの範囲:SLAが適用されるサービス(システム)の範囲を明確にします。
- サービスの内容:サービスの提供時間や問合せの受付時間、システム障害時の復旧時間などサービスの可用性や、システムの応答時間などのパフォーマンスに関すること、データやログの保持などの保全性などについて記載します。
- 役割や責任の所在:サービスにおける役割や責任を明確にする。その場合は提供者だけではなく利用者についても記載する必要があります。
- 契約事項が実行されなかった場合のペナルティー規定:目標を保証している場合にもし目標が達成しなかったら、ペナルティーとして目標未達率に応じて利用料金を減額する等の対処について記載したり、努力目標を設定した場合に目標が実現できなかったら、改善につながる施策を提示したりします。
- SLA変更手順:SLAは状況に合わせて見直すこともあるため、変更の手順について予め明記しておくと運用時にスムーズです。
上記以外でも予め合意しておいた方がいいサービスレベルがあればSLAに明記しておきましょう。
前回のRFPのときにご紹介したITコーディネーター協会のサイトにSLAの見本もあります。こちらをチェックするとよりイメージがわくと思いますので、是非チェックしてみてください。
●SLA見本(ITコーディネータ協会)
今回はここまで!次回もご覧いただけるとうれしいです!